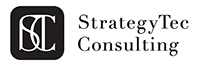株式会社ストラテジーテック・コンサルティング
2024年5月取材
※ 記事は過去の取材時のものであり、現在とは内容が異なる場合があります。
「手狭さ」と「採用計画」を見据えて
魅力ある大規模オフィスビルに移転
多角的な経営ソリューションを提供しつつ、先端技術の知見や次世代の事業トレンドを交えたコンサルティングサービスを展開している株式会社ストラテジーテック・コンサルティング。高いスキルを持つコンサルタントの入社を背景に急成長を続けている。今回は、オフィスの拡張移転を行った背景やオフィスコンセプトを中心にお話を伺った。

株式会社ストラテジーテック・コンサルティング
経営企画室
巳ノ瀬 拓紀 氏
Contents
- 戦略・DXコンサルティング事業にとどまらず地元経済の活性化もサポート
- オフィス移転の目的は手狭さの解消と採用活動を意識した立地改善
- 関連タスクを全体的に任せられ社内PMとして各社各部署間を奔走
- 新オフィスで目指したのはデザイン性と利便性の両立
- オフィス環境を整備したうえでハイブリッドワークを運用

エントランス
戦略・DXコンサルティング事業にとどまらず地元経済の活性化もサポート
大手コンサルティングファームの創業メンバーである三浦大地氏が、20年にわたる経験を活かして設立した株式会社ストラテジーテック・コンサルティング。2019年の設立からわずか4年足らずで、従業員数190名超の企業に成長している。ストラテジー(戦略)とテクノロジー(IT)を融合させた提案で顧客の事業課題をサポートするのが同社の特長だ。
「当社のコンサルティングは、ITの分野に特化しているわけではありません。クライアント様のニーズに応じて全社的な戦略から業務まで幅広いコンサルティングをご提供させていただいております」
短期間での事業拡大を可能にしたのは、経営戦略と大手企業との強いネットワークだ。
「どんなにスキルの高いメンバーが集まっても、それを発揮する場がなければ意味がありません。当社は経営陣などの人脈を最大限活用して多彩な案件を獲得してきました。それらの案件の面白さが有名コンサルティングファームのコンサルタントの関心を集め、採用活動に繋がっているのだと思います。そんなシナジーを持つコンサルティングファームは類を見ません。設立5期目に入り、他社との差別化を一層明確にしていきます」
今後、さらなる成長を目指しているのがSaaSプロダクト事業となる。それはデジタルイノベーションプラットフォーム「ContactEARTH(コンタクトアース)」を活用して、人と企業のイノベーションをサポートするものだ。今後、続々とプロダクトをローンチ予定ではあるが、現時点ではビジネスの課題を気軽にオンライン上で質問ができ、課題解決ができるチャット・インタビューサービスの「Quick」、社内外のDXエキスパートと出会える「Matching」の2つの機能を有している。どちらも多くの有識者が登録しており、数多くの知見の中から最適解を導き出すことを可能にする。
もう一つの事業が地方創生事業となる。本事業立ち上げのきっかけは、三浦代表の出身地である青森県弘前市活性化のために行ったプロジェクトだという。
「自治体との連携も強化しながら、今後は各大学からのインターン受け入れにもより注力していく予定です。事業を拡大することで各地方での雇用にも繋げられると思っています。加えてIT人材のためのコワーキング施設『Kadaru@Cafe HIROSAKI』(カダルカフェヒロサキ、現『KADARU+』(カダルプラス))の運営も行っています」
こうした弘前市での取り組みを知った秋田市から誘致の話があり、秋田事業所の開設へと繋がった。さらに、現在では仙台市でも同様の取り組みが行われている。偶然、東北地方に集中しているが、エリアを限定しているわけではない。今後も各地域に強い思い入れのあるメンバーを中心に全国地方都市の創生事業に力を注いでいきたいという。
同社が取り組んでいる地域給与格差是正の挑戦についても触れておこう。
「同レベルの仕事をしたとしても、『東京と地方では物価が違う』という理由で給与に大きな差が生じているのが現実です。しかし私どもは、働く場所がどこであろうと、給与はその人の労働の内容への対価として支払われるべきだと考えています。どこに住んでいても、東京と同様の給与を支払う。それによって格差を是正し、地方経済を刺激できればいいと思っています」
そんな急成長を続ける同社のオフィスは、増員の連続で瞬く間に手狭になっていた。
オフィス移転の目的は手狭さの解消と採用活動を意識した立地改善
旧オフィスは日本橋馬喰町に立地するオフィスビルだった。1フロア84坪。移転直前は、その面積に対し従業員が100名以上となっていたという。
「馬喰町という立地は交通の便こそ良かったのですが、肝心のオフィスがかなり手狭になっていました。今後の働きやすさを考えると、スペースの改善は取り組むべき課題だったのです」
そんな中、2022年12月に三幸エステートへ移転の相談をする。移転時期や希望面積、エリアなどを伝えると、その情報をもとに移転先の提案が行われた。
「迅速な対応でしたね。こちらから要望した資料の提出も早かったです。すぐに段取りをしていただき、物件の内見がスタートしました。八重洲や丸の内だけではなく、赤坂や渋谷といったエリアの物件まで幅広く内見しました。そうすることで、当社にとって最善のエリアは八重洲だと再認識できました」
最大の移転理由は手狭さの解消であったが、人材採用の拡大も念頭にあったという。
「常に優秀な人材を採用していきたい。そのためにはターミナル駅近くのオフィスビルに本社を構えることが必須だと考えていました」
提案を比較し、財務試算を行いながら最終的に選んだのは東京駅近くの大規模オフィスビルだった。
「ビルグレードは格段に上がりました。ランニングコストこそ上昇するものの、ブランディングや信用度など、プラスの効果が十分に上回ると判断したのです」
関連タスクを全体的に任せられ社内PMとして各社各部署間を奔走
移転先が確定したことで、具体的なオフィス構築のフェーズに入る。内装デザインは、数社の見積もりを確認しながら、パートナーとして協力関係を構築できそうな会社を選んだ。
「移転先のビルは、管理や工事、清掃、システムなど、細かく事業部が分けられています。ピーク時には十数社とのやり取りを行っていました。タイトなスケジュールでしたから、合意形成に時間がかかるのは避けなくてはなりません。外してはいけないポイントは確認しつつ、オフィス移転に係る全てのタスクを三浦社長に任せてもらえたことで、予定通りに進行できたと思っています。その分、自分が社内PMとしてパートナー各社や社内の部署間を奔走しましたが、逆にそのやり方でなければスケジュールに間に合わなかったかもしれません」
そうした社内外との打ち合わせや調整、決裁に半年近くを費やし、2024年1月に内装工事がスタートした。
新オフィスで目指したのはデザイン性と利便性の両立
経営側からのデザインの要望としては「高級感」「落ち着き」といったキーワードが挙がっていた。
「社外の方が利用するエントランス側は高級感が求められました。それでいて暗い雰囲気にしたくはないとの要望でしたので、デザイナーさんと一緒に頭を悩ませましたね。最終的に落ち着いたのが、今回使用しているブラウン系の色合いでした」
執務室側に関しては「従業員が働きやすいこと」以外に特に大きな要望はなかったため、従業員へもヒアリングの上、来客エリアと差別化するためにグレー系を基調とし、働く場ごとにメリハリのある色合いでまとめた。
「旧オフィスは居抜きで使用していたのですが、個人的には働きやすいオフィスでした。旧オフィスの良かった部分は新オフィスでも踏襲することにしました」
それでは新オフィスを紹介していこう。
エントランスは、木でつくられた和のテイストを組み入れたデザインとなっている。同社のロゴマークと受付システム、サイネージが一体となって配置されている。
「当初の案ではエントランスがもう少し広かったのですが、そこまで来客者が待つこともないだろうと。その分執務室に使う方が合理的という取締役からの意見もあり、面積を縮小して今のレイアウトとなりました」
エントランスを抜けると2室の社外用応接室が並ぶ。ガラス張りにしているが、打ち合わせの内容によっては内側からカーテンで目線を遮ることができる。

社外用応接室
「カーテンは自然をイメージし、配置は左右対称にしています。また、どちらの部屋にも、和のテイストが取り入れられた吸音パネルを取り付けました。ただ単に装飾として絵画などを飾るのではなく、全体の調和や実用性を保ちながらデザイン性を高めたかったのです」
応接室の正面にはソファとテーブルが置かれ、壁には同社のロゴマークをかたどったグラフィックアートが描かれている。

応接室正面
「これは壁紙やシートを貼り付けているわけではなく、直接壁に描いてもらいました」
執務エリアに入ると手前にオープンミーティングエリアが現れる。
「カウンターのソロスペース、半個室のスペース、ソファ席で構成しています。多目的でありながら働き方に合わせて使い分けることを推奨しています」

オープンミーティングエリア 半個室
執務室内にも、クローズドの会議室を配置した。これは社内会議用として使用される。
「会議室の名前は『NEPUTA』『TANABATA』『DONTAKU』『KANTOU』といった当社にゆかりのある都道府県を代表するお祭りの名前を付けています」
そのほか、窓際の景観が良い場所にソロカウンター席を配し、その周辺にソファ席やコーヒーカウンターを設けるなど、いくつものバリエーションを用意している。そして執務室の最奥にWeb会議用エリアを集中させた。

窓際カウンター席

執務室内ソファ席
執務室は大きく事業部と管理部に分類される。営業やコンサルタントなどの事業部はフリーアドレス、総務労務や財務経理などの管理部は固定席とした。新オフィスを構築するにあたっては、コンサルタントを中心にヒアリングを行なったという。

執務室全景
「彼らは普段からいろいろな会社のオフィスに訪問しているので、印象に残っている機能などを聞き出すことが目的でした。それ以外にも、三幸エステートさんのWebサイト『先進オフィス事例』コーナーを参考にさせていただきました」
コンサルタントからは、長時間座っても疲れにくい椅子にしてほしい、モニターを増やしてほしい、スタンディングで作業ができるスペースも用意してほしい、横になれてゆっくりできる休憩スペースを用意してほしいなどの要望があったという。
「予算も調整しながら最大限、全ての要望を取り入れました。休憩スペースも用意することにしたのですが、個室にしてソファーベットを置くだけでは使われない時間が多く、費用対効果が良くありません。スペースには常に家賃がかかっているという意識ですね。そこで結果的には、棚を用意して水や備品、防災グッズ置き場としての用途も付加し実現させました」
オフィス環境を整備したうえでハイブリッドワークを運用
移転後は従業員からの評価も高いという。
「綺麗で働きやすくなった、椅子がよくなって腰が痛くなくなった、会社までのアクセスが楽になったなどの声を多く聞きます。また、エリアを代表するオフィスビルに移転したこともあり、全体のモチベーションも上がっていますね。当社では『最低週〇日以上は出社すること』というような出社に関するルールは無いのですが、移転後は明らかに出社人数が増えています」
今後も、働き方はリモートと出社のハイブリッドワークで運用する予定だ。
「近年、リモート環境もだいぶ改善されてきました。中には自分でより良い環境に自宅を整えている従業員も多いですしね。確かに日常会話は減りますが、黙々と作業を進める業務や一人で深い思考をするような業務であればリモートでも何の問題もないと考えています。ただしハイブリッドですからリモート環境だけではなく、出社するオフィス環境も整備しなければ意味がありません。出社する意義を持つオフィスをつくり、そのうえで従業員はあくまで自らの意思でリモートか出社かを選択する。そんな環境がベストだと思っています」