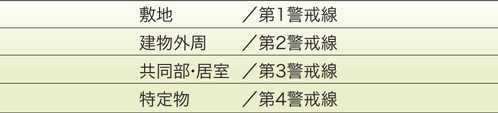S棟の建設を含む本社事業所のリニューアルプロジェクトにおいて、オフィスの設計・デザインとともに大きな課題となったのがセキュリティシステムの構築だった。
S棟の建設を含む本社事業所のリニューアルプロジェクトにおいて、オフィスの設計・デザインとともに大きな課題となったのがセキュリティシステムの構築だった。
「1階カフェをオープンなスペースにしたいと考えたとき、ほかの3棟を加えた事業所全体のセキュリティゾーンをどう設定するか、新たなルールづくりが必要になったのです」(小鷹氏)
簡単なのは敷地への出入りを完全にチェックし、その上で建物や部屋ごとの管理をする方法だが、それは不可能であることがわかる。
「正門だけでなく駐車場などからも敷地内に入れるようになっていたため、第1警戒線を厳重にするにはすべて高い塀で囲み、要所要所にガードマンを配置しなければなりませんでした。それではコストが増大してしまいます。そこで考えたのが、正門の受付をバーチャルなバリアとするアイデアでした」(小鷹氏)
仕組みとしてはこうなる。まず社内のセキュリティゾーンを次のように設定する。
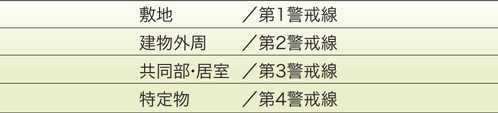
そして社員証を兼ねたICカード「Felica(フェリカ):ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方法」により、ゾーンごとの入退室管理を行うのだ。
「第1警戒線は物理的に区切らないものの、社員も来訪者も最初に受付に顔を出してチェックを受けないと社内に入れないというルールと仕組みをつくることで、心理的なバリアとしました」(小鷹氏)
S棟は目の前に受付があるので、そこを通らずにカフェオフィスに入るのは難しい。さらに入退室管理は第1警戒線から第2、第3、第4と順序通りに進まないと開錠できないダブルアンチパスバック方式を採用しているので、受付でチェックを受けなかった人がそれ以上奥に進入することは不可能だ。
「ダブルアンチパスバック方式では入室だけでなく退室までチェックするため、万が一、外部の人がオフィス内に入ったとしても、入室記録がなければ外には出られません。つまり、第2警戒線以降を厳しく管理することで、第1警戒線は心理バリアだけで済むのです」(小鷹氏)
社員にとって、オフィスを出入りするたびにカードによるチェックを受けなければならなくなる点は面倒ではあるが、慣れてしまえばそれほど不自由は感じないという。
「フェリカはカフェオフィスの支払いにも使えるので、かえって便利になった部分もあります。セキュリティの必要性は充分にわかっており、このシステムによって会社が守れるのですから、私自身は導入に大賛成でしたね」(宮本氏)
社員が喜ぶオフィスをつくることが帰属意識やモチベーションの向上に
そのほか、寺岡精工のS棟における工夫の数々を紹介しておこう。
ユニバーサルレイアウトの採用
ノンテリトリアルは導入せず、すべて固定席だが、異動のときは人だけが動いてデスクの配置は換えず、組織変更に柔軟に対応できるようにしている。また島型対向のデスクはパーテーションで自由にサイズが変えられるタイプ。現在は6mの机3人でシェアするのが標準だが、機器のチェックなどをする技術者は広げることができ、その点でもフレキシブルな利用が可能。
ショールームとしてのカフェオフィス
自社製品である自動計量販売システムを使ったグラムデリ(グラム単位でおかずを買える)や浄水システム、オゾン除菌脱臭洗浄機、POSレジ、Edy精算システムなどをカフェオフィスに設置し、ショールームとしても活用しているだけでなく、社員に製品を身近に感じてもらうようにしている。歴史的な商品である「はかり」も展示し、帰属意識を高める工夫をした。
「食堂」に見えない社員食堂
昼食時間を除けば厨房との間をデザインされたドアで仕切り、見えなくする。
「食事以外の目的でこのスペースを使おうと思っても、厨房が見えたら、なかなか気持ちの切り替えができません。このため、新規通常は食堂にいると感じないような工夫をしました」(
小鷹氏)
多目的に使えるカフェテーブル
カフェオフィスのテーブルは小鷹氏がデザインしたもので、自由に合体が可能。このため大人数の打ち合わせやパーティーなどにも利用できる。
パワーミーティングができる会議室
カフェオフィスの一画にガラスパーテーションで区切った会議室を2部屋設置した。場所の利を活かして昼食を兼ねたパワーミーティングにも使われている。
どの部分においても、目的を明確にして設計・デザインしただけに、ユーザーの評価はかなり高くなっている。
「とにかく、社員たちが『いいオフィスができた』『会社に来るのが楽しくなった』と喜んでくれるのがうれしいですね。これからの企業は、社員満足度を高めるための投資を積極的にしなければいけません。それは採用などにも効果的に働くわけで、決して無駄なコストではないのです」(山田氏)
この事例をダウンロード
バックナンバーを一括ダウンロード